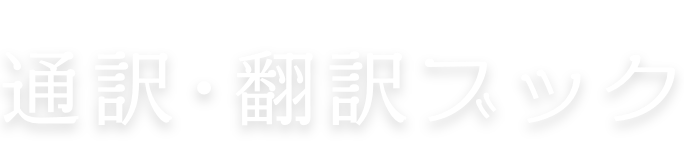大阪・関西万博で個性溢れるパビリオンが話題となったオーストリア。
『通訳・翻訳ブック』では開幕1年前、準備の様子を特集でご紹介しました。
今回はプロジェクト責任者アルフ・ネテックさんのインタビューを通じて、万博での挑戦と成果を振り返ります。
大阪・関西万博を振り返って
パビリオン完成までの長い道のり
――2025年4月に大阪万博が開幕しました。何年も準備されてきて、いよいよ開幕となった時は、どんなお気持ちでしたか。
ネテックさん(以降、ネ):たくさんの時間と労力を注いできたので、少しナーバスになっていましたね。私たちのパビリオンに対し、皆さんがどういう反応をされるのかが全く予想できませんでした。おかげさまで非常に盛況で、9月初旬には来場者が100万人を突破しました。小規模パビリオンにしては、素晴らしい成果を上げているのではと思います。
――前回お話を伺った際はまさにパビリオンの建設中で、記事には完成イメージのイラストを掲載しました。とてもユニークで美しいデザインなので、実際はどうなるのだろうと思っていたのですが、実物もまさにあのイラストそのものだったので大変驚きました。
完成されるまでに、特に大変だったことや苦労されたことなどありましたら、お聞かせください。
ネ:これは非常に難しい質問ですね……。たくさんのハードルがあって、本当に全てが大変でしたが、強いて言うと五線譜のリボンでしょうか。と言うのも、これはオーストリアで制作し、船で大阪まで運んで組み立てたのですが、なかなか日本政府の許可が出ず、何度も何度も申請が必要でした。オーストリアと日本では木造建築に対する考え方が違いますし、今回は初の試みなのでとても慎重にもなったのでしょうね。例えばネジひとつにしても、オーストリア製と日本製では異なるため、そこから説明する必要がありました。また、万が一雪が降っても、リボン部分に絶対積もらないという前提を満たさないといけないので、その点を証明するのも苦労しましたね。
満足度98.9%。来場者から寄せられた声
――皆さんのご尽力のおかげで、私たちはあの美しいパビリオンを目にすることができたのですね。ところで、ネテックさんは来場者の様子や感想などを見聞きされる機会はあるのでしょうか。
ネ:ええ。私は皆さんとコミュニケーションを取るのが好きなので、できるだけパビリオン内を回るようにしているんです。ピアノの自動演奏時、「赤白赤(あかしろあか)」というキャラクターが登場するのですが、毎回毎回「可愛い~!」という声が上がるので面白いですよ。また、撮影した画像をSNSにアップして私に見せてくれる方もいて、皆さんに楽しんでいただけているなと実感しています。
他にも毎日800人ほどの来場者にアンケートをしているのですが、全体の98.9%の方が「非常に満足」と回答されていて、私たちもとても嬉しく思っています。パビリオンの雰囲気や展示、レストランの食事、スタッフのおもてなしなどを評価してくださる方が多いです。
ゴールは「一緒に未来を作っていく」こと

――私も見学させていただきましたが、パビリオン全体が1つの交響曲のように感じました。入館前の五線譜から第1楽章が始まり、展示が進むにつれ楽曲が展開していくようで、コンパクトながらとても楽しめました。
ネ:それは嬉しいですね。まさにパビリオン全体をストーリーのように構築して、木造の五線譜から館内のデジタル映像とサウンド、そしてまた木造の展望台へと変化していくのをお見せしたかったんです。展示でも、伝統的な技術とイノベーションを架け橋とした、新たな価値や可能性などを提示できたのではと思います。
――実際に来場者が体験したり参加できる展示が多いのも印象的でした。特に、来場者がメロディーを考え、AIとコラボして1つの新しい曲を作っていく企画が興味深かったです。私達ひとりひとりが未来を作っていく当事者なのだと実感できましたし、自己と他者、デジタルとアナログなど、コラボして皆で一緒に作り上げていく、というメッセージのようにも思いました。
ネ:ええ。まさにそれが私たちの求めているゴールです。パビリオンのテーマは「Composing the Future(未来を作曲)」ですが、私はさらに「Composing the Future Together」、この「Together」が最も大切だと考えています。この地球上の誰もが、特別で大切な、尊重されるべき存在です。政府間や企業間だけでなく、私たちひとりひとりが互いに理解し合い、一緒に未来を作っていく、という気持ちを持ってもらえたらと思っています。
万博はボーダレスな世界を体感する絶好の機会
――パビリオンはテーマごとに配置されているそうですが、オーストリアのそばにカナダ、中国の隣にクウェートなど、実際の地理上とは全く異なるのでとても新鮮でした。また、パビリオン間を多くの人が自由に行き交っていて、国と国との距離がなくなったような感覚になりました。
この万博は、前回ネテックさんがお話しされていた「国や文化が違っても皆が同じ惑星のもとに生きている」ということを実感できる貴重な機会だったのではないでしょうか。
ネ:そうですね。多くの方が、ボーダレスな世界を体感されたのではと思います。私としては、各国のパビリオンも大屋根リングのようにひとつに繋げたいくらいでしたけれど。「異なる文化や風習に触れ、他者への理解を深める」「今この地球で起こっている様々なことが、決して他人事ではなく、自分とつながっていることなのだと認識する」……。今回の万博は、多くの来場者にとって、そんな気づきや意識変革の絶好の機会になったのではないでしょうか。

――ところで、万博ではパビリオン以外にも多くのお取り組みをされましたね。5月のナショナルデーでは、ウィーン少年合唱団の合唱や、モーツァルトの愛用したバイオリンによる演奏なども非常に話題になりました。
サイマルでも通訳のサポートをさせていただきましたが、ファン・デア・ベレン大統領はじめ多くの方が来日されて、オーストリアと日本の絆もさらに深まったのではと思います。
ネ:ええ。パビリオンでも紹介しているように、両国間には長い交流がありますが、日本で2年半、この万博に関わってきて、両国の友好関係がさらに深まっていくのを肌で強く感じています。個人的にも友人もとても増えましたし、距離こそ離れていますが、文化面や気質など、両国にはとても共通点が多いとあらためて思いました。
閉幕後。その先の未来へ
2030年リヤド万博に向けての課題
――パビリオンはスペースに限りもあり、テーマも絞っていらしたと思います。今回は残念ながら実現できなかったものや今後の課題などはありますか。
ネ:イベントやショーを開催できるステージがあると良かったですね。屋外ステージでウィーン舞踏会のダンスイベントを開催し、多くの方に参加していただきましたが、万博会場の共用スペースなのでめったに利用できないんです。国を紹介するには、実際にステージで音楽やダンスなどをお見せするのが一番だなと思うので、それが実現できなかったのはとても残念です。
他にも学ぶべき点がありました。
先ほどお話しした来場者アンケートでは、ネガティブな評価として、待ち時間や待機列の長さを挙げる方がいらっしゃいました。想定の10倍以上の人が来てくださったので、体験型展示やレストランでも長時間お待たせしてしまい、本来のおもてなしをご提供することができなかったと感じています。もっと多くの方に並ばず入っていただけるよう、次回万博の課題としてしっかり持ち帰りたいと思います。
オーストリアと日本で築いていく共創社会
――それでは最後にお伺いします。オーストリアと日本はこれまで150年以上の国交がありますが、この万博を機に、どのように関係を発展させていきたいとお考えですか。
ネ:今回の万博は未来社会の共創がテーマです。両国は、高齢化社会など共通の課題も多く、お互いに共有し、学んでいける点が多いのではないでしょうか。様々な分野でより強固な関係を築いていけると思いますが、個人的には、特に数学、物理、化学、IT分野での女性研究者の進出について共に取り組んでいければと考えています。まだまだ検討できることも、今すぐ実践できることも多いはずですから。
万博を1つのステップとして、さらなる関係を築き、友情をはぐくみ、コミュニケーションを重ねていくことが、ソリューションにつながる大きな力になると信じています。
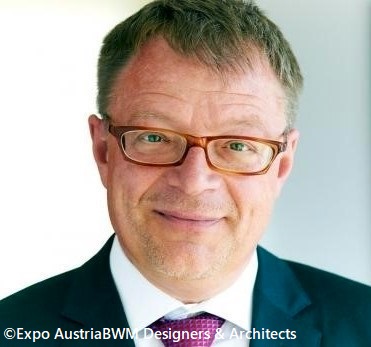
オーストリア連邦産業院万博事務局代表 兼 政府代表代理
ICT(情報通信技術)分野でキャリアをスタート。Kapschグループをはじめとするグローバルテクノロジー企業やヨーロッパを代表する子供靴メーカー・リヒター社等で経営幹部を歴任。独立後は、様々なプロジェクトでマーケティングやコミュニケーション担当として活躍するかたわら、オーストリア国内外の様々な大学で教鞭も執っている。

まずはサイマルへ
「大切な会議やイベントなので、経験豊富な通訳者・翻訳者やスタッフにサポートしてほしい」「通訳者・翻訳者としてやりがいのある仕事をしたい」―― そんな時は、ぜひサイマル・グループにお任せください。