
本連載では、現役の会議通訳者・池内尚郎さんが同時通訳の実践的技法を紹介していきます。ご自身が、日々の実践を通じて気付いたことを、通訳者の方や通訳者をめざす方々に向けて「実践則」としてまとめたコラムです。第5回は「聴くのではなく『聞け』、訳者よりも『役者』になれ」です。
日本語では「きく」という行為を表す場合、二種類の漢字が使われる。「聞く」と「聴く」だ。「聞く」は音や声などが自然に耳に入ってくることを意味し、「聴く」は積極的に注意深く耳を傾けることをいう。物音は「聞く」が、音楽は「聴く」だ。
では、英語はどうか。英語にも二種類の単語がある——"hear"と"listen"だ。
BBC Learning Englishというサイトで調べてみると、"hear"の対象は"sounds that come to our ears, without us necessarily trying to hear them(必ずしも聞き取ろうとするものではない状態で耳に入ってくる音声)"、"listen"は"paying attention to sounds that are going on(流れている音声に注意を向けること)"となっている。
面白いことに、このサイトで紹介されている"hear"と"listen"の例文も、先に挙げた日本語の例文と同じ「物音」と「音楽」が使われている。つまり、「聞く」と「聴く」、"hear"と"listen"にはそれぞれ鏡のような対照関係があるということだ。
ここまで二つの単語の意味の違いを解説したのは、通訳において「きく」という作業は「聞く」なのか「聴く」なのかということを考えてみたいからだ。結論を言えば、通訳者は話者の音声を"listen"ではなく"hear"している。
そんな馬鹿な、と思われるかもしれない。そこで一介の通訳者の戯れ言と一蹴されてしまわぬように、大家にご登場いただく。ダニッツァ・セレスコビッチ——ソルボンヌ大学の通訳翻訳高等学院(ESIT)の学長も務めた欧州屈指の通訳者であり、通訳者にとって座右の書といってよい"Interpreting for International Conferences"(『会議通訳者 国際会議における通訳』研究社)の著者である。
意識的に聴きながら別のことは話せない
セレスコビッチはこの本の中で、即興で演説する話者と同じような思考プロセスを、同時通訳者もなぞっていくと述べた上で、次のように解説する。少し長いが大事な点なので引用する。なお、主語のHeは通訳者のことである。本書は1978年初版のため、gender neutralな表現が定着する前の時代であることにご留意いただきたい。
セレスコビッチの主張は明快だ。同時通訳者は話者の言葉を「聴く」のではなく「聞く」といっている。それも「聞く」のは「単語」ではなく「意味」である。別の箇所で、セレスコビッチはこんなことも言っている。
同時通訳というと「聞きながら話す」という作業が神業のように驚嘆されることもある。しかしセレスコビッチのこの言葉にあるように、一言一句も聞き漏らすまいと神経を研ぎ澄ませて聴いているときは、どんなに有能な通訳者も訳出を続けていくことは難しい。もちろん同時通訳の現場ではそのような「集中的傾聴」は発生するので、そうした瞬間でも訳出を放棄しない技量を身につけなければならない。しかし「集中的傾聴」と「自然な訳出」との両立をずっと続けることは不可能だ。
一方、話者の発する単語ではなく意味を理解し続けることができれば、聞きながら話すことは大きな負担にならない。だから、同時通訳の成否は、話者の発言の意味を耳から頭にしみ込ませる状態をどれだけ持続できるか、他方いかに細かな単語レベルで足をすくわれない状態をつくり出すかにかかっている。その工夫をどのようにするか、それは別の回で説明したい。
「同時通訳者はアナリストやマインド・リーダー(読心術者)であり、オウムではない」(…the simultaneous interpreter is an analyst or mind-reader, not a parrot.)——セレスコビッチのこの一文に、同時通訳おける「理解」とは何か、そのすべてが表現されている。
自分の言葉で語る
次は同時通訳における「表現」とは何かである。話者の言葉を訳すことではないか、と即答が来そうだが、ちょっと待ってほしい。前半の「理解」のところで、通訳者は「単語」ではなく「意味」を聞くと述べた。そうすると、アウトプットである「表現」も当然のことながら意味を表現することになる。では「単語を表現する」ことと「意味を表現する」こととはどう違うのか。
一番違いが分かりやすいのは、音声を聞きつつテキストを読みながら通訳をする、いわゆるサイト・トランスレーションだろう。経験者は同意してもらえるはずだが、テキストを読みながら通訳すると音声のスピードに追いつけなくなり振り落とされてしまうことが少なくない。これは、単語を読んで文章を理解し、それを別言語に置き換える作業は、音声を聞いて意味を丸ごと腹落ちさせるのに要する時間よりはるかに長くなることが原因だ。
これが「単語を表現する」ことの意味だ。同時通訳者は、このようなやり方では訳出を継続させることはできない。たとえばword for wordの訳を作ろうとすれば、どこかの段階で破綻してしまう。持続可能な方法ではない。
では、持続可能な方法はどういうものか。それは、通訳者自身がスピーカーになることだ。会議場で通訳者は黒子のはずなのに、スピーカーになるとはどういうことか。読者には驚きだろう。でも、このように考えてほしい。通訳者が訳出を自然な形で続けていくことができるとすると、それは話者のストーリーの意味を理解して、それを自分の言葉、自分の表現力で再生できているときである。「自分の言葉で語る」——これはもはや一人のスピーカーである。もちろん、好き勝手にやっていい訳はない。通訳者はあくまでも話者の代理人である。代理人が話者を無視して独自の抑揚や、口癖の言葉を入れ込めば、これはもはや代理人ではなくなる。「自分色」を出しすぎるのは厳禁だ。しかし、通訳者はその存在を消してはならない。セレスコビッチはさすがだ。
話者・聴衆・通訳者の三者対話
だから、通訳者が介在する会議では話者と聴衆という「二者対話(dialogue)」ではなくて、そこに通訳者も入る「三者対話(trilogue)」(セレスコビッチ)となる。こんなことを言われると、通訳者には荷が重い。しかし、これは通訳者も一人のパブリック・スピーカーとして並び立つくらいの話術の力を鍛えろという励ましと捉えたい。そして、パブリック・スピーカーとしての実力を備えるということは、自分の表現力を駆使して自在に通訳することができるということである。

禅宗に公案(こうあん)というものがある。修行僧が禅師から授かる問題のことで、それは一見まったく意味がわからない判じ物のようものだ。修行僧はその答を考え抜いた末に、禅師を訪ね自分なりの結論を伝えるが、「違う」とはねつけられる。それを何度も繰り返す中で、修行僧は自らの力で真の答を見つけ出していく。今回のテーマは、この公案のようなものである。
聴くのではなく「聞け」。訳者よりも「役者」になれ。
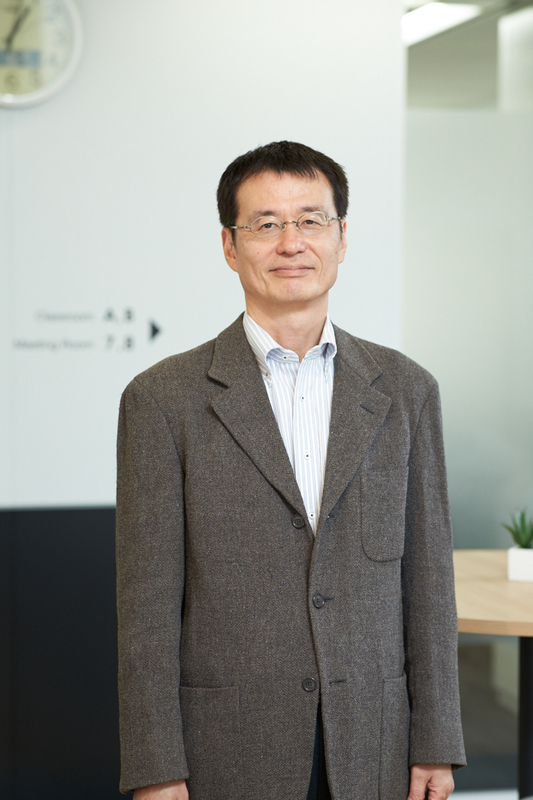
サイマル・インターナショナル専属通訳者。上智大学外国語学部ロシア語学科で学ぶ。国際交流や国際政策に関わる仕事の後、サイマル・アカデミーで学び通訳者に。政治・経済・文化・科学技術など幅広い分野で活躍。同校通訳者養成コース会議通訳クラスで後進の指導にあたる。
【続きはこちらから】訳し下ろしの同時通訳術 第6回
として働くなら
サイマルへ
サイマル・グループでは、世界との交流を共に支える通訳者・翻訳者を募集しています。あなたのキャリア設計や就業スタイルにあった働き方で、充実したサポート体制のもと、さらなる可能性を広げてみませんか。

